
2019.12.01
競うということ
Text : Chihiro Taniguchi
12 月に入り、みぞれやあられ、雪が舞う日が続いてたこともあり、誘っても戸外で遊ぶことが少なくなってきたあけび組の子どもたち。この日も室内で手持ち無沙汰にしている人がちらほら。何かしかけが必要だなと思い、お相撲大会を開催することを呼びかけました。
11 月頃から数人が相撲を取る姿もあったことも、その理由にありました。すると、次々に参加表明をする人が現れ、クラスの 1/3 の人が名乗りをあげてトーナメント戦をする流れになりました。

取り組みが始まると、戦うモードに入り、自らを鼓舞するように体の様々な部分を叩きながら気合いを入れる姿、雄叫びをあげる姿などがありました。あまりにも自然なその姿をみて、本能なのか?と思わせるほどでした。『見合って見合って』と行司が場を整えると、一気に目つきが変わり、真剣な表情に。取り組みがいくつか進み、IくんとKくんの対戦の順番がきました。お互いに闘志溢れる様子で立合いました。土俵際、体を反らせて粘ったIくんでしたが、押し出されてしまいました。負けたIくんは悔しさのあまり涙が溢れ、次第にその悔しさは大きくなっていく様子でした。部屋の角にうずくまり、対戦を思い出し『どうして負けちゃうんだー!』と叫びながら自分の気持ちと向き合っている姿がありました。
よく考えてみると、やまのこでは運動会など競う機会が少ないので、勝ち・負けの文化とは距離があります。あえてそのような環境を作っていなかったのではなく、優先したいと考えるものが他にあったことで結果的にそうした機会がなかったのです。しかし、改めて機会を作ってみると、多くの子が戦うことに積極的で様々な方法で士気を高める姿があったり、真剣勝負の結果を受け止め自らの感情に向き合う様子や豊かな表現をする姿がみられると共に、誰かを応援してその結果を一緒に喜んだり、讃えたり、慰めたり、元気づけようと声をかけたり、労ったりと、仲間の存在を確認できる機会にもなっていました。日常の中にもこのように喜び・悔しさ・緊張感・チャレンジする気持ちなどが発生する環境が時として必要なのかもしれないと感じました。そもそも、勝つ・負けるが存在することを承知した上で、挑戦するということが子どもたちにとって、どのようなニーズから生まれているのでしょうか。力を試してみたいのか?何かを確認したいのか?好奇心なのか?本能なのか?これからも、子どもたちのニーズから環境を設定していきたいと思います。


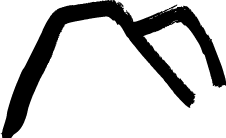

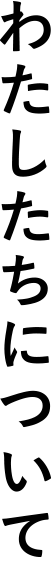
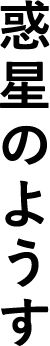
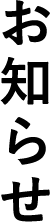
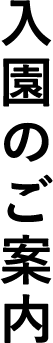
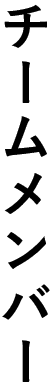
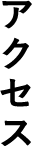
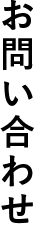
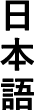
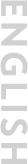



 PREV
PREV