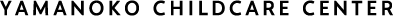2019.03.03
節分プロジェクト—赤い顔のお客さんは、どう迎えられ、どこに行ったか?
Text : Tomoko Nagao
節分の日、やまのこには赤い顔のお客さんがやってきました。この日がどのように迎えられ、そして子どもたちがどんな受け止め方をしたのか。問いから始まり、徐々に形がつくられていったそのプロセスはアトリエワークそのもののように感じられました。
問1: どんな節分にする?鬼とは何か?
節分の1ヶ月ほど前から、職員間では節分をどう迎えるかが話し合われていました。1-2歳児だけだった昨年は、小さな人たちを怖がらせる必要はなかろうと、鬼のいない節分を迎えたやまのこ。しかし今年は3-5歳児もいる。今回はどんな節分にしようか。
今年は鬼を迎えよう。でも鬼って何だ?鬼は怖い(もしくは悪い)ものか?いや全ての鬼が怖いわけじゃない。怖い/悪い鬼をやっつけろ!豆をぶつけて追い払え!というストーリーは本当か?追い払うならボールを投げるように鬼に向かって豆を投げるが、豆”撒き”と言うからにはパァーっと下から上へ豆を撒くのでは?鬼は異界からやってくる者なのでは?使者として異界の存在を私たちに知らせるものなのかも?
鬼を迎えようとなった途端、様々な問いが生まれてきました。職員合宿や会議でも意見が交わされ、問いが熟成していきます。
節分は「季節を分ける」と書きます。三寒四温という言葉に現されるように、緊張と弛緩の繰り返しによって季節は変化します。そして、季節の変わり目は、そのまま身体の変わり目でもあり、この変化に体調を崩して亡くなる人もいたことから、ある種の「緊張」を人々は求めたのではないか。それらが現在の「節分の鬼」へと発展していったのではないか。つまり、「緊張」を生み出す「異界=よくわからないもの」が鬼の正体であり、怖いものである必要はない。
最終的に、私たちが大切にしたいのは、節分を通して異界の存在を感じること。鬼である必要も、怖がらせるためのものでもなく、「異界からやって来た何かわからないもの」と出会うことだ、と導き出されていきました。
問2: 何かわからないものをどうやって表出させるか?
次なる問いは、異界からやってくる「何かわからないもの」をどう表出させるか。
写真家シャルル・フレジェのYOKAI(妖怪)シリーズの写真や、沖縄のニライカナイ、民俗学者折口信夫が唱えたマレビトなども参照され、日本には古来から異界の存在と共存する文化があることを思い出しながら、職員それぞれの異界の想いがイメージから形に変換されていきました。
何かわからないものをつくって置いておくのはどうか。急に現れると驚いてパニックになる人もいるので、迎え入れるスタイルがよい。誰かが舞うのはどうか?日に日に、異界を表象する品々が職員から持ち寄られました。澄んだ音の鳴る鈴、山から採ってきた木の枝、韓国で見つけたお面、浜辺で見つけた浮き玉、異界を感じさせる動き(踊り)…など。イメージを共有しながらアイデアを差し出す共同制作でした。
そして迎えた当日
2月3日。雨あがりで、ほどよい風が吹いていました。子どもたちが「パラッ、パラッ〜、鬼は外 福は内〜」と豆撒きを始めると、それに誘われるかのように、かすかな鈴の音と笙のような音と共に赤い顔をした“なにものか”が庭からやってきました。庭で舞う光景を窓越しに見つける子どもたち。”なにものか”は、その後各クラスに入って再び舞い、しばらくするとふわーっと外へ去って行きました。


やまのこ保育園 homeのふき(0歳児)・わらび(1.2歳児)、やまのこ保育園のうるい(0歳児)・こごみ(1.2歳児)クラスでは、泣きじゃくる子も、「おかあさんー」と求める子も、ぎょっとした顔で静止して目だけ向ける子もいました。”なにものか”が部屋に入ってきた瞬間、異界な存在が自分たちのエリアに入ってきたと感じたのでしょうか、「わ、入って来た…!」と多くの子どもはズズズと寄り合いくっつきあっていましたが、きょとんとした顔でトコトコ近づき、近距離で見つめあうかのように迎え入れた姿も見られ、異質なわからないものへ、怖さではなく好奇心でもって近寄り、新たな出会いを十分に経験しているようでした。
あけび組(3-5歳児)では、一目散にトイレに隠れ鍵をかけた子、ぼくはこわくないもんと言いながら近寄っていく子、保育者にしがみついて震えている子、半信半疑ながら興味深そうにじっと見つめる姿。「なんか音聞こえる」「片足だけ靴下履いてないね」「風に吹かれて嬉しそうだよ?」「あけびの部屋初めてだから探検しているのかな」「手と足があるから人なのか」節分=鬼=怖いものだと思っていた子は「何もこわいことしてこないね」と、多くの言葉が聞かれました。

さらに、”なにものか”が去った後、あけび組の子どもたちは興奮気味に、今のはなんだったんだ?と話し始めました。鬼?いやツノがなかった!サンタさん?天狗?いつの間にか「赤い顔をしたお客さん」と呼ばれ始めていました。また来てくれるかな?くねくね山に行ったら会えるかな?探しに行こう!とSくんの提案に、私もぼくもと、何人かが繰り出していきました。「さっき赤い顔したお客さんが来たんだけど、どこに行ったか探してるの。見なかった?どっちに行ったか知ってる?」やまのこ保育園homeまで行って訪ねるとあっちの方とSpiber社の方角を教えてもらった子どもたち。Spiber社に到着して、園児の父にも尋ねてみたけど「ここにはまだ来てないなあ」と。よくわからないものとの出会いの経験から、どこに行ったのか、また会えるのか、探しに行こう、と自ら確かめに向かう次なる動力が生まれ、突き動かされるように探求を始めた子どもたちの姿がありました。
わからないものと向き合うこと
職員が問いを熟成させ、探りながら形を生み、そこから子どもたちの更なる探求が始まった。この節分の一連の出来事は、やまのこ全体が、問いを契機にうごめきながら、私たちなりの保育を作りだしていったプロセスだと思われます。
「名前もなく、だれも知らない、生まれたてのなにものかがただそこにいることの静かなざわめきを増幅させる」(齋藤陽道展「なにものか」2015年/3331Arts Chiyoda/展覧会テキストより)
写真家齋藤陽道の言葉のように、教育の場で、私たち大人もわからないものと向き合い、子どもと共に、誰も知らない、生まれたてのものを捉えていく感度を高め、探求の渦を増幅させていった、そんな節分プロジェクトでした。
RELATED


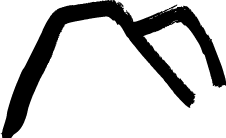

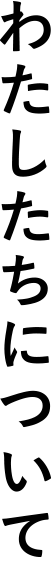
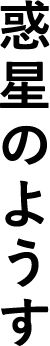
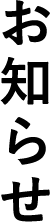
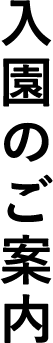
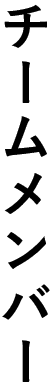
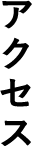
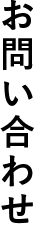
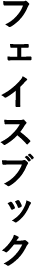
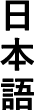
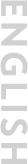
 PREV
PREV