
2025.02.05
小麦畑からクッキーへ
Text : Chihiro Taniguchi
昨年度から、やまのこに保育補助兼お菓子づくりや酵母の専門家として勤務いただいている高見尚子さんと会話していた時のことです。
「子どもたちと小麦畑に行って自分たちで刈り取ってこれたらおもしろそうですよね!その小麦でお菓子を作ってみるとか…」という話題から、約1か月をかけた小麦プロジェクトが始まりました。
かねてより自分たちが食べる作物が育っている環境を訪問してみたいと思ってはいたのですが、農家さんとのコネクションなども探りつつも、なかなか踏み出せないでいたところに具体的な提案が飛び込んできたので、”今だ!”という感覚を携えてこのプロジェクトがスタートしました。
やまのこの子どもたちは日常的に月山高原で作られた小麦を使ってクッキーやケーキ、ピザなどを作っています。彼らにとって産地に行って素材に触れ、生産している方に出会うというということは、作物のストーリーを感じるということです。
子どもたちに「食べ物を食べるということは、それが自分の一部になる、統合するということ」という趣旨の話をわたしはよくします。数式のように足されて引かれてただ食べて排出するだけでなく、身体の中のあらゆるものを構成する一部となるということを子どもたちにも伝わるように話しています。自身の身体の一部となる作物のストーリーに触れるということは彼らの世界を広げ、巡り巡って自分を大切にできる、自分を取り巻く環境を愛おしいと感じられるきっかけになるのではないかと思っているからです。
【知る・刈り取る・干す】
今年の5月-6月は涼しい日が多く、小麦の生育がゆっくりな年だということで、月山高原の小麦畑を訪れた日は刈りごろまで1週間ほどという感じでした。
予定していた月山高原での収穫は叶いませんでしたが、里に近い小麦畑に移動し、刈り取りをさせてもらいました。
到着するなり、広大な面積を埋め尽くす黄金色の小麦たちを眺めて思わず「これ小麦?!」と想像していたものとは違ったことに驚きを見せていました。近づいてみると風に揺られ、穂と穂が擦れ合って音を立てていることに気がつきます。
その様子をみて「なんかかわいい」と呟く子も。
”小麦”というワードは知っているものの、日常的にクッキーやケーキ、パンを作る時に使っている”粉”とは、あまり結びついていない様子もありました。
各々、持参したハサミで1本ずつ刈り取ります。彼らの目にはどの小麦も違って見えるのか、一本一本選んでは「これ!」と決めて刈り取っているように見えました。数えきれないほどの中から「これいいな」と感覚的に選んだものだけを集めていくのは楽しく、心地の良い作業だろうとその様子を眺めていました。
どんどん刈り取っていくと、切った茎の中が空洞になっていることを発見!節になっている部分を切り落としてその場で早速ストローとして使ってみることにしました。
Mさんがコップに入れたお茶を茎のストローで吸ってみると…
「!!!飲める!!!」
目を見開いて「すごい!ストローじゃん!」と興奮気味にレポートしてくれました。
すると、我も我もと人だかりができてストロー作りが白熱し、その場はストロー工場へと発展したのでした。
yamanokoに戻った後、刈り取ってきた小麦を協力して東家に吊るして干します。どうやって干せば落ちないか、みんなで意見を出し合っている様子でした。
干しながら穂束からポロポロとこぼれ落ちた粒をそのまま食べている子たちがいて、どんな味だろうと気になり、私も試しに食べてみるとなんと甘い!次に、爪で割ってみるとなんと水分がたっぷり出てきたのです。
そして子どもたちに「今の味、覚えておいてね、1週間後味を比べてみよう」と約束したのでした。

【脱穀・製粉】
1週間後…
干していた小麦を竿から外し、約束通り味を確かめてみました。すると「あんまり甘くない」「この前の方が味がした」「硬すぎるよ」という声が聞こえてきました。 たった1週間”干す”という工程を挟んだだけでこんなにも変化があることに私自身驚きました。
そして、農家の叶野さんに足踏み式の脱穀機をお借りして早速脱穀に挑戦してみます。
初めは、機械の性質を知ることに必死で、保育者も子どもたちもオロオロ…
一人では踏み込めないので、2-3人の力を集結させて踏むのですが、これがなかなか…息が合わず止まってしまったり、逆回転になってしまったりなど、難儀する時間が続きました。

しかし、試行錯誤を重ねるうちに子どもたちから「そうだ!こんな感じでやればいいだ!」とか「せーのって言ったら踏んでね!」と掛け声が入るなどしてチームごとの工夫によって効率良く脱穀できるようになったのです!穂束は20束以上あったのですが、残り3-4束になった頃には、開始時の半分の作業時間で完了するほどになっていました。
なにより、一緒に踏んだメンバー同士で協働したことの喜び、コツを掴んだ手応え、どんどんテンポよく進められる心地よさなどを感じている子どもたちの表情が印象に残っています。
子どもたちが一つひとつ手応えをもって学びを得る過程に居合わせられたことは保育者として幸せな時間だったなと振り返ります。
さて、脱穀をしたのはいいが、穂束から外した粒には籾殻や藁くずも混じっている状態でした。これをなんとか粒だけにしなければ、製粉できません。
どうしたものか…
先人たちはどのようにしていたのかを調べてみると、唐箕(とうみ)という機械を使って選別していたことがわかりました。送風機で風を送り軽い籾殻や藁くずを飛ばすという単純な構造です。
これらをヒントに、やまのこでは扇風機を使ってみることにしました。
掬い取った粒たちを高い位置から落としながら風をあててみると、粒だけが真下に落ち、その他のものは遠くに飛ばされていきます。その作業を繰り返していく中で、Iちゃんが突然「そうか!軽いから飛ばされるんだ!」と発見したことを言葉にしていました。
一見すると何度も何度も同じことを繰り返しているようでしたが、Iちゃんは様々なことを考えたり、仮説を立てたり、やり方を少しだけ変えてみたりしながら小麦の粒に触れていたのだということがわかりました。
身の回りを取り巻く出来事について、私たち大人にとって新鮮さはさほどなく「そうだよね」になっていることも多いですが、このようにして子どもたちが原体験から自然界の法則のようなものを発見し、その後の遊びや暮らしに取り入れていく様子をみていると、体験から獲得していく手応えある学びによって、自分を取り巻く世界の捉え方はおもしろい方向に変化していくのではないかと思います。

そしていよいよ製粉です。
このプロジェクトを動かし始めた当初は「石臼で挽けたら楽しいかも」と呑気なことをいっていたのですが、在来作物研究者の江頭先生(山形大学農学部教授)に問い合わせたところ…
「小麦は作物の中でも最もといっていいほど硬く、昔はロバに挽かせるほどでした。よほど大きな石臼あるいは硬い材質の石臼でないと製粉できないと思います。石臼が削れて石臼がいたむので、かしてくれる人を探すこと難しいと思われます。」
とのことでした。
またまた壁にぶつかり一筋縄ではいかないプロジェクトです。ところが、尚子さんが家庭用粉砕機をお持ちだったので、その機械で小麦を粉砕できるかどうかをメーカーに問い合わせてくれたのです!
結果、「外皮が硬く、粗めの仕上がりになるかもしれませんが、粉にはなります。」とのことで、今回はその機械を使ってみることにしました。
しかし、そんなにも硬いのであれば、せっかくだから小麦の硬さを体感してみるのもいいのでは?!と考え、園庭の石や保育室にあるアクリル樹脂の積み木を使って原始的な方法で粉にしてみる実験もしてみることにしました。
まずは人力で潰してみると、なかなか潰れてくれず、ようやく半分に潰れたと思ったらそれ以上は小さくすることはできませんでした。粒から小粒になった程度でした。やはり硬い!
次に粉砕機で試してみます。
ここまでの体験を経て、粉砕機に入れられる粒たちをみて、Tちゃんが「なんかドキドキする~」と呟いていました。
その時私も「うん!わたしもドキドキする!やっとここまできたね!」とすかさず返していました。
大きな音は振動と共に保育室中に響き渡るほど勢いのあるものでした。機械自体は小さめでしたが、かなりのエネルギーを要しながら粉砕していることが音と振動から伝わります。
いざ粉砕機の蓋を開けてみると「うあ~!!本当に粉になってる~!!」粒から粉になる過程を目の当たりにして納得感のようなものを含んだ反応でした。
粉砕機は小さいので、全ての粒を粉砕するのにくりかえし機械にかけたのですが、4回目くらいに差しかかると、子どもたちは「もういい」と言って別の遊びを始める子がほとんどでした。あんなに感動していたのに…と一瞬思ったのですが、子どもたちにとっては粉になっていく過程は理解し、おもしろさは体感したものの、何度やっても結果は同じ。そこが「もういい」につながったのだと感じました。
【調理】
粉にした直後から「はやくクッキー作りたい!」と期待を膨らませていたこともあり、尚子さん主導の元、製粉したての小麦でクッキー作りが始まりました。
作るのは3種類
① 粉砕機かけた小麦100%
② 粉砕機かけた小麦50% 庄内小麦ゆきちからオレンジ50%
③庄内小麦ゆきちからオレンジ100%
*粉砕機で製粉した小麦は全粒粉、ゆきちからオレンジは外皮を除いた白い部分の粉

パッと見ただけでSちゃんは「色もにおいも全然違う!」と気づいていました。
実際にこねるときにも、①の生地はボロボロで形が崩れてしまい成形するのにも難儀でした。
全ての生地を成形して並べてみると、一見あまり違いはわからなくなっていましたが、実際に手を動かして作った子どもたちには区別できるものになっていた様子でした。
クッキー作りには参加していなかった保育者に対しても一つひとつの違いや配合を説明している子もいました。
そしていよいよ焼き上がったクッキーを食べてみます…
おいしい!はもちろんのこと、子どもたちにとっては3種類全て味が違うこと、それぞれによって好みが別れるということに出会っていました。
「こっちの方がサクサクしてる」「こっちの方が好き」と口々に感想を言い合っていたのが印象的でした。誰もそれを否定せず、ありのままを表現し「〇〇ちゃんはこっちの方が好きだって!」と美味しいものを囲んで笑顔で報告しあう時間。
自分たちで収穫し加工してそれを味わい、自分の感じたままを誰かに伝えることができるこの空間はとても平和だと感じました。
このプロジェクトを始めたきっかけは、収穫~加工まで全ての工程に携わることで自分たちを取り巻く世界が広がればいいなというものでした。
全ての過程を体感してみて感じているのは、子どもたちは保育者たちの想像を超えた学びを自らの力で獲得していくことができるのだということ、保育者が環境や機会を作ることとの相互作用で、湧き上がる知的好奇心を最大限に発揮しつづけるのだということです。
子どもたちと共に学ぶという姿勢で今回のプロジェクトを進めてきましたが、言葉通り共に、いやそれ以上に多くのことを保育者側が学ぶ時間となりました。
実際、生産者の方にお会いしてつくり手さんの言葉で作物について情報を得ること、「いっぱい食べて大きくなれよ~!また来るの待ってっぞ!」と温かみを感じることができたことも貴重な時間でした。
急速な農業人口の減少、就農者の高齢化も相まって、この子たちが大人になる頃には農家さんという存在は遠く離れたものになっている可能性もあります。
だからこそ今、作物を作っている人を身近で感じること、食べものの成り立ちに少しでも触れること、この鶴岡という土地の美しさや美味しさが原風景として彼らの中に残っていくことを大切にしたいと思っています。
このプロジェクトに限らず、やまのこでの毎日の暮らしは、このような考えを元に編み上げているものも少なくありません。
このプロジェクトが始まる前までは「小麦」というワードで思い浮かぶのは白い粉一択だったと思います。
これら一連の活動を経て「小麦」というワードから彼らが想像する情景は、黄金色の小麦畑であったり、脱穀機にかける穂束だったりと様々な小麦の姿が浮かび上がってくるようになったのではないでしょうか。
~高見尚子さんより一言~
粒のときも、製粉したあとも、どんなタイミングも、どんな感じかな、と食べてみる! としてた子が多かったなと振り返っています。
きっと粉だけしか知らなかったら粉を食べようと思わなかったと思うのですが、粒から粉にしたあと、Nちゃんは粉を食べて「あまい!おいしい! 」と話していたんです。 それが印象的でした。


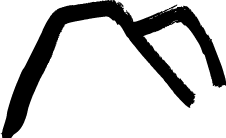

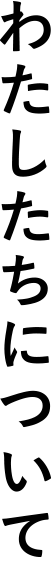
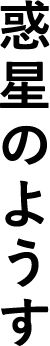
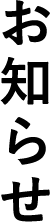
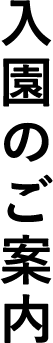
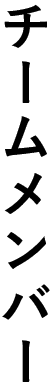
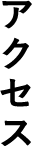
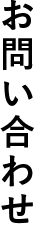
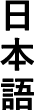
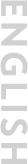












 PREV
PREV